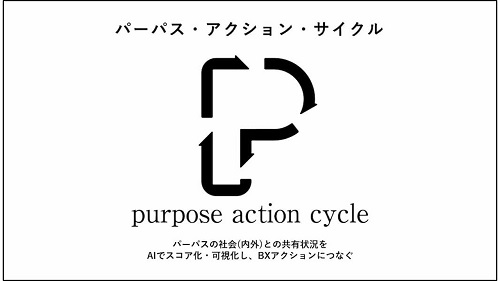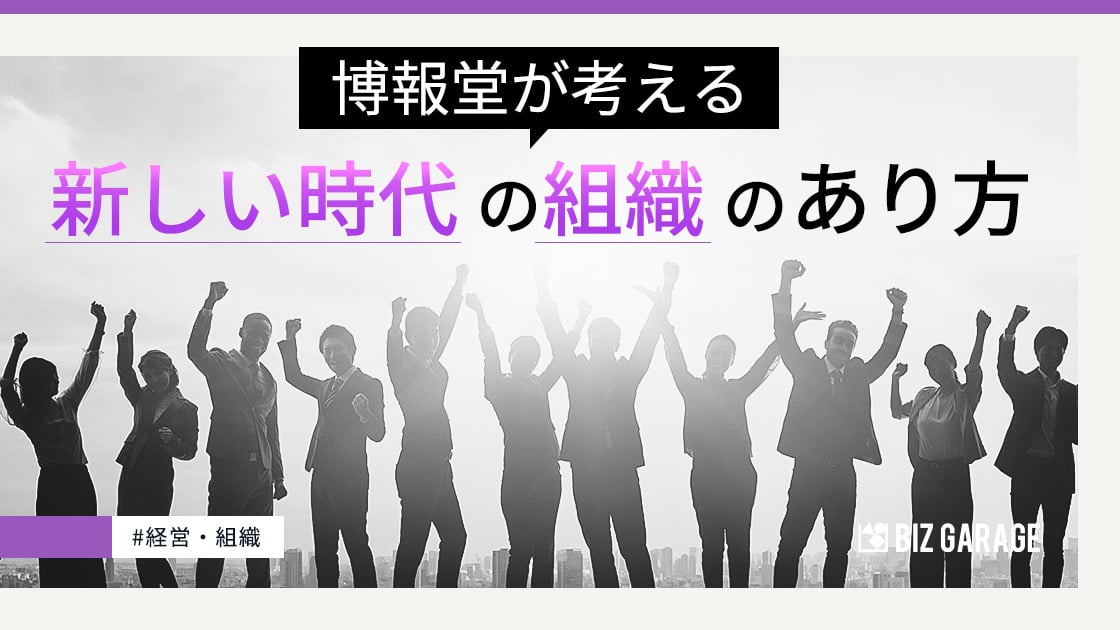革新が求められる時代に、社会的価値と経済的価値を両立させながらスピーディーに質の高い変革を推進していくためにはどうすれば良いのか。その解決策として「デザイン経営」に関心を持つ人が多い一方で、結局何をやれば良いのか分からない、という声が多いのも事実です。
そこで2024年12月12日、「デザイン経営」をテーマにウェビナーを実施しました。ウェビナーでは、HAKUHODO DESIGNのブランドコンサルタントが登壇。デザイン経営の具体的な取り組み事例について語ってもらいました。多くの方にご視聴いただきましたので、その模様をお伝えします。
後編の本記事では、西川株式会社の成功事例、デザイン経営導入のプロセスなどをご紹介します。
登壇者
HAKUHODO DESIGN ブランドコンサルタント 和泉 舞
目次
HAKUHODO DESIGNが提供する8つのソリューション
和泉 こうしたデザイン特有のアプローチを活かして、HAKUHODO DESIGNでは、以下の8つのソリューションを提供しています。
「企業理念(PMVV)策定」
従業員や経営層への共感から始めて、未来洞察を取り入れたり(バックキャスト)、従業員と経営層とのワークショップで進めて(共創プロセス)、多くの人の意見を吸い上げながら(複雑性から)新しい価値を見出していく、というようなプロセスをイメージしていただければと思います。
アクションの詳細で言うと、未来社会における自社の存在意義を見出すとか、自社の将来のありたい姿を描く、自社の個性(DNA)を探索する、自社の提供価値を見つめ直すということなどが挙げられます。
「VIデザインシステムの策定」
このソリューションは、考えとカタチを往復するというデザイン特有のアプローチを生かした、主にアートディレクターとデザイナーが活躍するソリューションです。
企業理念に基づく思想を視覚的に表現し、一貫性を持って伝達していく役割を担います。VI、ブランドカラー、タイポグラフィ、あるいはそれらの使用法をルールブック化したり、経営や事業に関わる、誰もが視覚的にブランドを表現できるようなシステムを作ったりしていくことが主なアクションになります。
「企業理念・VIとの連動による中期経営計画の策定浸透支援」
このソリューションは、企業理念・VIと中計が連動していないケースが見受けられる場合、ここをしっかりと連動させて両方が浸透していくような支援ができないかということを考えて、提供しています。
文字通り、企業理念・VIと連動した中計の策定を支援するということと、また、従業員への浸透のための施策を行うことが主なアクションです。
「インナー/アウターブランディング」
これは元々、HAKUHODO DESIGNがやってきた事業と近いアクションですが、ブランドの思想を右脳的左脳的に情報伝達していきます。または五感的体験的アプローチで伝達します。
「組織文化醸成」
これは、定めた企業理念を従業員が自分ごと化して、行動化に繋げたり、あるいは組織文化として定着させていくソリューションです。
「デザインリサーチによる新事業・ブランド・商品開発」
このソリューションは、従来のリサーチ手法とは異なる、デザインリサーチという手法を用います。顧客と社会の潜在的なニーズを探索したり、課題解決のみならず全く新しい機会を発見したり、あるいは、試行錯誤を繰り返しながらアイデアをブラッシュアップしていくことを支援します。
「デザインリーダーシップ」
これは、従業員向けの能力開発プログラムのようなもので、共創型リーダーシップ、クリエイティブリーダーシップと言い換えることができます。従業員の主体性を高めることや、共創する仲間を創る力、創造性を引き出すといったアクションがメインです。
「パブリックデザイン」(ソーシャルデザイン)
和泉 最後のソリューションは、自治体や官公庁、公的組織を対象としたものです。システミックデザインという手法で、複雑な社会課題に取り組みます。他に、マルチステークホルダーとの共創支援も行います。とくに公共施策、公共政策のステークホルダーは多岐に渡るので、それらの人々の共創を支援することが主なアクションになります。
デザイン経営を導入することによる期待成果は様々ですが、課題感や困りごとに合わせて、必要な解決策を提示することができます。
総括すると、デザインによる解決策を導入することで、企業が抱えている経営・事業課題を解決すると同時に、価値創造・企業文化醸成を行うことで、自社の持続可能性を叶え、理想的な未来社会の実現に少しでも近づいていくことが、デザイン経営を導入することの意義です。
また、日本デザイン振興会の定量調査からは、デザイン経営に積極的な企業ほど売り上げが高く、コアなファンを多く獲得していること、従業員からも愛される企業へと変化を遂げていることが数字で実証されています。
従来型経営とデザイン経営の違いについて整理してみると、従来型経営では、売上げや利益の拡大が経営を駆動してきたのに対し、デザイン経営では、経営の中心に、「企業理念」や「新価値創造」「理想的な未来社会の実現」「持続可能性」などがあります。
顧客との関係性やリーダーシップ、組織文化、ビジネスプロセス、イノベーションにおいても、両者の違いは分かれますが、デザイン経営を導入すると一気に移行するというものではなく、徐々に重心が移っていくイメージです。
西川株式会社の「デザイン経営」導入事例

和泉 HAKUHODO DESIGNでは今まで、デザイン経営の導入をさまざまな企業に提案してきましたが、その中でも代表的な西川株式会社の事例をご紹介します。
450年以上の歴史を持つ西川グループは、1940年代から80年近く3社に分かれて経営を行ってきましたが、 2019年に経営統合するにあたり、時代変化にあった新たな価値を創出すること、グループとして組織の求心力を高めること、統合後の西川ブランドを社内外に浸透させることが課題として出ていました。
HAKUHODO DESIGNで実施したアクションは、企業理念の策定、すなわちパーパスと新価値の策定、VI策定、組織文化醸成、インナーブランディング、アウターブランディングを通して、企業統合によって新たに生まれる西川株式会社の今後の競争力・成長力の基盤および起点作りです。
なかでも、パーパス・新価値の策定では、「ふとんの西川」という商材そのままを表現したコアバリューを見直し、ウェルネスが重視されている社会環境を考慮した上で、「睡眠ソリューションの西川」という、新しい価値を探索。コアバリューの転換を図り、新たなパーパスを策定しました。
デザイン経営の導入プロセス

和泉 デザイン経営導入のプロセスは、組織や事業の状況や課題に応じて複数想定されますが、代表的な事例としては、いまご紹介した西川のように、企業理念・VI策定を起点とする場合と、新規事業や既存事業の変革を起点とした場合があります。
前者の場合は、
- 企業理念・VI策定
- インナー向け企業ブランディング・アウター向け企業ブランディング
- 組織文化醸成
- 事業ブランディング
というステップで進めます。また、後者の場合はこの逆で、
- 既存事業・新規事業のブランディング
- 社員の主体的な行動や意識の変化を促進
- 組織文化の醸成
- 新たな企業理念を策定
という流れになります。

それぞれの進め方はどんな企業に向いているのかという点に関して付け加えると、今までご相談いただいた経験から、前者は、人材や予算に余裕がある程度あり、企業のDNAや価値観が従業員に浸透しているが言語化・明文化できていない企業、既存事業などでブランドという無形資産が生む効果を経験済みである企業などが着手しやすいものと思われます。
一方、後者は、短期的な売上を重視せざるを得ない状況の企業や、経営や事業運営をトップダウンで行っている企業などに向いていると思われます。
デザイン経営アセスメント

和泉 HAKUHODO DESIGNでは、デザイン経営導入の最初のステップとして、経営や事業におけるデザイン活用の現状と課題を把握するために、デザイン経営アセスメントのアンケートにご回答いただくことを推奨しています。また無料でアンケート結果の分析を行って、課題に適したソリューションのご紹介もしますので、ぜひご相談いただきたいと思います。
プロフィール
 和泉 舞
和泉 舞
株式会社HAKUHODO DESIGN
東京外国語大学卒、東京大学大学院総合文化研究科博士前期課程修了。広告会社2社を経て2013年に博報堂入社。ストラテジック・プラニング職として、トイレタリー・化粧品、家電、飲料・食品・嗜好品、アパレル、外食産業、流通などの業務経験が豊富。支援提供領域は、新商品開発からコミュニケーション戦略、新規事業開発、事業戦略・経営戦略まで多岐にわたる。近年では、生活者や得意先従業員との共創による企業理念の策定や組織文化醸などに従事。2023年11月より現職。
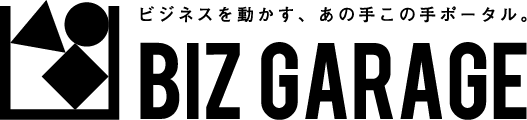
BIZ GARAGE 編集部
ビジネスをとりまく環境の大きな変化により、最適な手立てを見つけることが求められる現代。
BIZ GARAGEのコラムでは、生活者の心を動かし、ビジネスを動かすために、博報堂グループのソリューションや取り組みのご紹介、新しいビジネスの潮流などをわかりやすく解説しています。