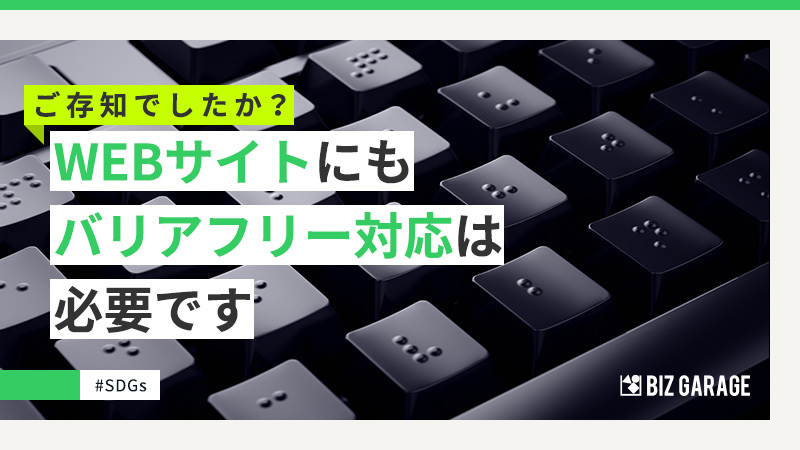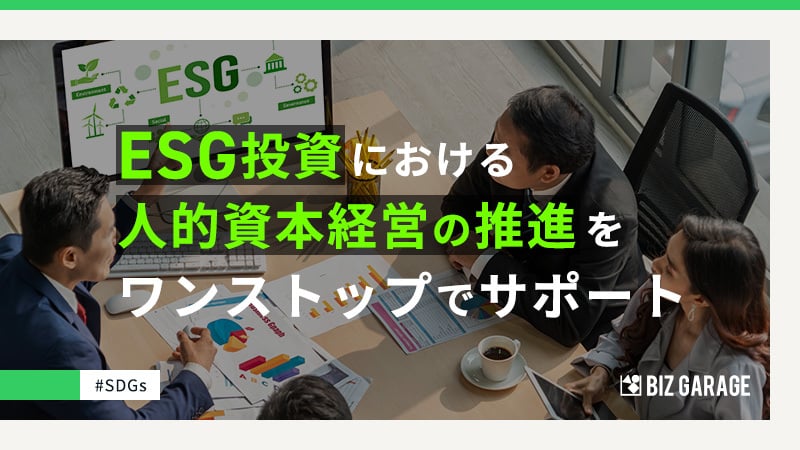2024年の4月から改正障害者差別解消法が施行されます。事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が、単なる「努力義務」からいよいよ「義務」に変わるのです。
「合理的配慮」の内容は、障がい特性・それぞれの場面・状況に応じて異なります。このため、各企業は、それぞれの具体例等をあらかじめ確認しておき、柔軟な対応が必要です。特にWebサイトにおいてWebアクセシビリティを確保することは、必須になるでしょう。
本記事では、Webアクセシビリティの概要、メリット、高める方法、欠かせないポイントを紹介していきます。
目次
Webアクセシビリティとは何か
Webアクセシビリティとは、高齢者や障がい者を含む全ての人が、年齢や身体的条件に関わらず、PC、スマートフォン、タブレット、ゲーム機など様々なデバイスを通じて、Webで提供される情報やサービスに安心してアクセスし、利用できる状態を指します。
近年では、老若男女を問わず誰もがWebサイトの情報を閲覧できますが、その際、どのような方も等しい情報を見られるようにする必要があります。そのため、Webサイトの運営に当たっては、全ての人が簡単に利用できるようにWebアクセシビリティを確保しておくことが欠かせません。
博報堂グループでは、企業のダイバーシティ推進を支援する「WEBアクセシビリティ改善ソリューション」を提供しています。ユニバーサルデザインのリーディングカンパニー「ミライロ」と「博報堂アイ‧スタジオ」、「博報堂」の3社でタッグを組み、サイトの診断から改訂業務まで、ワンストップでご支援します。⇒サービス紹介ページはこちら
Webアクセシビリティ対応を行うことが当たり前の社会に
Webサイトやスマホアプリなどを利用するのは、健常者だけではありません。高齢者や障がいを持つ方など、視覚や聴覚に不自由があり、PCやスマホの操作にハンデを持つ人も日常的に利用します。
総務省の平成24年の調査によると、既に視覚障がい者の91.3%がインターネットを利用していました(出典:総務省「障がいのある方々のインターネット等の利用に関する調査研究」 )。また、同じく総務省の令和5年の調査によると、令和4年の高齢者のインターネット利用率は、60代が86.8%、70代が65.5%となっております(出典:総務省 令和5年版情報通信白書 年齢階層別インターネット利用率)。
こうした方々は、音声読み上げのアプリケーションを利用 して、Webサイトやアプリを「耳」で「閲覧」しているのです。 一方で、多くの企業は障がい者の利用を前提としたWebサイトを作っていません。目の見えない方・見えにくい方に向けたWebアクセシビリティに対応している企業は、現状約1割にとどまっています。
ウェブアクセシビリティ基盤委員会(Web Accessibility Infrastructure Committee (WAIC) )が実施した 「一般企業におけるウェブアクセシビリティ方針策定と試験結果表示の実態調査(2019年2月)」(出典:ウェブアクセシビリティ基盤委員会)によると、調査対象サイト224事例のうち、視覚障がい者への配慮事項を記載しているサイトは24事例にとどまっています。
つまり、現状では多くのサイトが音声読み上げのアプリケーションに対応できない設計で、1割程度のサイトしかWebアクセシビリティを確保していないことがわかります。
一方、アメリカでは既に、ADA法(障がいを持つアメリカ人法:Americans with Disabilities Act of 1990)により、Webアクセシビリティへの未対応が訴訟に発展するケースも急増しています。日本企業も、欧米を中心とする海外進出先で指摘を受けるリスクが高まっているのです。
こういったグローバルな広がりを受け日本でも、昨年9月のデジタル庁設置に伴い施行されたデジタル社会形成基本法に、全ての国民にWebアクセシビリティを保証する旨が明記されました。また、2013年に制定された障害者差別解消法も、2021年5月に改正法が成立し、前述のとおりこれまで民間事業者には「努力義務」にとどまっていた合理的配慮が「義務」とされたのです。
そしていよいよ、2024年4月1日から改正障害者差別解消法がスタートします。これまで努力義務だからと十分対応できていなかった事業者は、Webアクセシビリティがまだ確保できていない部分にしっかり取り組む必要があるのです。
博報堂グループでは、企業のダイバーシティ推進を支援する「WEBアクセシビリティ改善ソリューション」を提供しています。ユニバーサルデザインのリーディングカンパニー「ミライロ」と「博報堂アイ‧スタジオ」、「博報堂」の3社でタッグを組み、サイトの診断から改訂業務まで、ワンストップでご支援します。⇒サービス紹介ページはこちら
Webアクセシビリティが確保できている状態
そもそも「Webアクセシビリティが確保できている」とは、どのような状態を指すのでしょうか。ここからは、Webアクセシビリティが確保できている状態について、代表的な以下4点を解説します。
- 誰でも操作でき・情報が伝わること
- キーボードのみで操作可能なこと
- 色の区別による判断がないこと
- 文字以外の情報が充実していること
それでは、1つずつ確認していきましょう。
誰でも操作でき・情報が伝わること
1つ目は、誰でも操作でき、情報が伝わることです。Webアクセシビリティが確保されているサイトとは、障がいの有無にかかわらず、全ての人が容易に操作でき、記載されている情報を確認して理解できるサイトです。
これは、年齢や技術的なスキル、使用しているデバイスの種類に関係なく、全てのユーザーがWebサイトにアクセスし、その機能をフルに活用できるようにすることを意味します。そのため、記載された内容のテキスト読み上げ機能、高コントラストモードの提供、簡単なナビゲーションなど、多様なニーズに対応するための設計が必要です。
障がいの有無に関わらず、多くの人が使いやすいことは、Webアクセシビリティが確保できている状態の重要なポイントです。
キーボードのみで操作可能なこと
2つ目は、キーボードのみで操作可能なことです。マウスを使うのが困難な人にとっても、キーボードのみでWebサイトの全機能を利用できるよう、サイトを設計することが大切です。
例えば、サイトに含まれているリンクやボタン、フォームフィールドなど、マウスクリックが必要な要素にタブキー使用を許可すれば、キーボードのキーでアクセスできます。
キーボードのみで全ての操作ができれば、障がいを持つユーザーや高齢者をはじめ、マウスの使用が難しい人も、Webサイトを簡単かつ効率的に利用できるでしょう。
色の区別による判断がないこと
3つ目は、色の区別による判断がないことです。色の区別による判断をなくすことで、色覚特性に差があるユーザーも、Webサイトに記載されている情報を正確に理解できるようになります。
例えば、色に加えて、テキスト情報や記号を使用して情報を伝えることです。従来エラーメッセージが赤色で表示されていた場合は、今後はさらにエラーであることをテキストでも明示すべきです。
企業はより広い範囲のユーザーに対応し、誰もが平等に情報を得られるようにWebサイト設計を見直すことが大切です。
文字以外の情報が充実していること
4つ目は、文字以外の情報が充実していることです。Webアクセシビリティを確保する上で、文字以外の情報が充実していることが不可欠です。
例えば、画像に代替テキストを提供する、ビデオに字幕や手話通訳を追加する、音声コンテンツに逐語録を用意するなどの対応が必要です。
上記対応により、視覚や聴覚に障がいのあるユーザーも、Webサイト上の情報を完全に理解できるようになります。誰でもさまざまなコンテンツにアクセスできるようになり、全てのユーザーがより豊かにWeb利用ができるでしょう。文字情報だけでなく、多様な表現方法を取り入れることは、Webアクセシビリティにおいて欠かせません。
博報堂グループでは、企業のダイバーシティ推進を支援する「WEBアクセシビリティ改善ソリューション」を提供しています。ユニバーサルデザインのリーディングカンパニー「ミライロ」と「博報堂アイ‧スタジオ」、「博報堂」の3社でタッグを組み、サイトの診断から改訂業務まで、ワンストップでご支援します。⇒サービス紹介ページはこちら
Webアクセシビリティを確保するメリット
ここからは、Webアクセシビリティを確保するメリットについて、以下3点を解説します。
- 全ての人が使いやすいWebサイトになる
- 多様なデバイスから利用できる
- 検索精度が向上する
それでは、1つずつ確認していきましょう。
全ての人が使いやすいWebサイトになる
1つ目のメリットは、全ての人が使いやすいWebサイトになることです。Webアクセシビリティを確保すれば、障がいの有無にかかわらず全ての人が使いやすいWebサイトを実現でき、サイトの使いやすさ、覚えやすさ、読みやすさが向上します。
例えば、適切なコントラスト・フォントサイズに改善して、年齢や技術的なスキル・使用するデバイスの種類に関係なく、同じようにサイトを見られれば、全てのユーザーにとって使いやすいサイトとなります。従来より広い範囲のユーザーがWebサイトを効果的に利用できるようになり、情報やサービスの利用機会も平等に提供されるでしょう。
多様なデバイスから利用できる
2つ目のメリットは、多様なデバイスから利用できることです。多様なデバイスとは、スマートフォン、タブレット、PC、さらには音声認識デバイスやスクリーンリーダーのような特別な技術を使用するデバイスも含まれます。
従来のPC基準に従って設計されたWebサイトは、異なる画面サイズや入力方法に柔軟に対応しておらず、デバイスが変わると見え方も変わり、使いにくい、一部の機能が使えない、などの事態に陥っていました。
Webアクセシビリティを確保することで、ユーザーがどのようなデバイスを使用していても同じように情報にアクセスできるようになります。そのため、Webサイトはどのようなデバイスからでも利用しやすくなり、誰もが同じ情報を見ることができます。Webを利用するデバイス種類が増えることは、企業にとってもメリットがあることです。
検索精度が向上する
3つ目のメリットは、検索精度が向上することです。Webアクセシビリティを確保すると、Googleなどの検索エンジンのクローラーがWebサイト内容をより効率的に理解しインデックス化する作業が容易になります。
これは、アクセシビリティ対策として取り入れられる明確な構造・適切な見出しタグの使用・代替テキストの提供などによって、サイトの構造がクローラーにとっても理解しやすくなるためです。Webアクセシビリティ確保によるサイト改善は、結果的にサイトの検索エンジン最適化(SEO)に貢献し、検索エンジンからの評価も上がるでしょう。
Webアクセシビリティは、検索を利用する全ての人の利便性を向上させるだけでなく、より多くのユーザーにWebサイトを見てもらえるようになるでしょう。サイトの利用者だけでなく、サイト運営者にとっても大きなメリットがあるのです。
博報堂グループでは、企業のダイバーシティ推進を支援する「WEBアクセシビリティ改善ソリューション」を提供しています。ユニバーサルデザインのリーディングカンパニー「ミライロ」と「博報堂アイ‧スタジオ」、「博報堂」の3社でタッグを組み、サイトの診断から改訂業務まで、ワンストップでご支援します。⇒サービス紹介ページはこちら
Webアクセシビリティを高める方法
ここからは、Webアクセシビリティを高める方法として、 代表的な 以下4点を解説します。
- 文字のコントラスト調整
- スペースやタブを多用しない
- 画像への代替テキストの追加
- 字幕追加
それでは、1つずつ確認していきましょう。
文字のコントラスト調整
1つ目は、文字のコントラスト調整です。文字のコントラスト調整とは、テキストや画像上の文字が背景色とはっきり区別できるように、コントラスト比を高めることを意味します。
適切なコントラスト比を確保することで、視覚障がいのあるユーザーや高齢者、さらには直射日光など光の条件が悪い環境でデバイスを使用している人も、Webサイトの情報を読みやすくなります。Webサイトの文字のコントラスト調整などのデザイン変更は、全てのユーザーが情報を効率的に受け取れるようにするために重要です。
スペースやタブを多用しない
2つ目は、スペースやタブを多用しないことです。Webアクセシビリティを高めるためには、単語の途中で不要なスペースや改行を避けるなど、テキストを統一することが重要です。不必要なスペースやタブを使用すると、スクリーンリーダーなどの支援技術を使用するユーザーは、テキストの読み取りが困難になる恐れがあります。
例えば、スペースやタブを多用すると、スクリーンリーダーが不適切な箇所でテキストを区切ってしまい、内容の理解が難しくなるでしょう。テキストの構造を明確にし、情報を正確に伝えるためにも、スペースやタブの使用は慎重に行う必要があります。
画像への代替テキストの追加
3つ目は、画像への代替テキストの追加です。Webアクセシビリティを高める1つの方法として、「画像への代替テキストの追加」があります。
代替テキストとは、画像を埋め込む時に情報タグを入れるものです。画像の内容・機能・画像がページ内で果たす役割などを代替テキストに入れていきます。代替テキストがあれば、画像が伝える情報や目的をテキスト形式で説明できるようになり、視覚障がいのある方や画像が読み込めない状況の方も、画像の内容を理解できます。
また、代替テキストは、スクリーンリーダーやテキストベースのブラウザを使用するユーザーにとっても重要です。正確で意味のある代替テキストを提供することで、全てのユーザーが同じ情報に平等にアクセスできるようになるでしょう。
字幕追加
4つ目は、字幕追加です。字幕追加は、聴覚障がいのある方が映像の内容を理解できるようにするだけでなく、非母語話者や音量を出せない環境にいる方にも役立ちます。
字幕は映像の音声部分をテキスト形式で提供し、会話や背景音、重要な音響効果などの説明を含んだものが望ましいです。字幕があることで、映像コンテンツはより幅広いユーザーに受け入れられやすくなります。
また、SEO(検索エンジン最適化)の観点からも有利に働くことがあり、コンテンツの検索を高める効果も期待できます。字幕の追加は、全ての人にとって使いやすく情報にアクセスしやすいWeb環境を構築する上で重要な役割を果たすのです。
博報堂グループでは、企業のダイバーシティ推進を支援する「WEBアクセシビリティ改善ソリューション」を提供しています。ユニバーサルデザインのリーディングカンパニー「ミライロ」と「博報堂アイ‧スタジオ」、「博報堂」の3社でタッグを組み、サイトの診断から改訂業務まで、ワンストップでご支援します。⇒サービス紹介ページはこちら
Webアクセシビリティ向上に欠かせないポイント
ここからは、Webアクセシビリティ向上に欠かせないポイントについて、以下2点を解説します。
- 法令内容と障がい特性等の理解
- 定期的な改善
それでは、1つずつ確認していきましょう。
法令内容と障がい特性等の理解
1つ目のポイントは、法令内容と障がい特性等の理解です。Webサイトやアプリケーションが全てのユーザーにとって使いやすくアクセスしやすいものであるためには、法令内容だけでなく、障がいのある人のニーズに対する深い理解が必要です。
障がいのある人が直面する主な課題、それらに対する合理的配慮の形態をあらかじめ把握しておくことで、円滑なコミュニケーションと効果的なWebアクセシビリティ対策が可能になります。例えば、視覚障がい者にはスクリーンリーダーの使用を考慮した設計、聴覚障がい者には字幕や手話通訳が必要です。Webを通じてやり取りしていくためには、法令や障がいに関する理解が不可欠です。
定期的な改善
2つ目のポイントは、定期的な改善です。Webアクセシビリティ確保に取り組む上で、定期的な改善は欠かせません。Webサイトやサービスのアクセシビリティは一度きりの取り組みで完結するものではなく、技術の進化、ユーザーニーズの変化、新たな法令やガイドライン導入など、時間とともに変わる要素に随時適応する必要があります。
そのため、定期的にサイトをレビューし、ユーザーからのフィードバックを積極的に収集して、改善ポイントを特定し、対応策を実施することが重要です。継続的に改善していくことで、Webサイトは全ての人にとってより使いやすく、アクセスしやすいものになるでしょう。
博報堂グループでは、企業のダイバーシティ推進を支援する「WEBアクセシビリティ改善ソリューション」を提供しています。ユニバーサルデザインのリーディングカンパニー「ミライロ」と「博報堂アイ‧スタジオ」、「博報堂」の3社でタッグを組み、サイトの診断から改訂業務まで、ワンストップでご支援します。⇒サービス紹介ページはこちら
アクセシビリティ対応のその先・ユーザビリティやUXの向上を
Webアクセシビリティ対応を求める社会的な機運の高まりがある中で、対応の基準として日本にはJIS X 8341-3(高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ)があります。まずはこのJIS規格にしっかり対応し、規格に基づいた診断を行うことが一般的に求められる基準です。
しかし、このJIS規格に対応しているかどうかを網羅的に課題発見するためには、既存のアクセシビリティチェックツールだけでは限界があります。そのため、専門家の目視による診断を行うことが望ましいです。さらに上記のJIS規格診断をして改善を行った上で、実際に障がいのある方によるユーザーテストを行うと、アクセシビリティだけではないユーザビリティやUXの向上につながるでしょう。
診断から実装までワンストップで対応
博報堂はユニバーサルデザインコンサルティングのリーディングカンパニーである、株式会社ミライロと、WEBサイト制作を担うグループ会社である博報堂アイ・スタジオと協働して、WEBアクセシビリティ改善ソリューションを開発いたしました。
前述の環境変化への対応および、Webアクセシビリティ対応だけにとどまらず、その先のユーザビリティやUXの向上をクライアント企業にお届けします。
ミライロ社がWebアクセシビリティ診断。改善コンサルテーションまでを担当し、その上で、博報堂アイ・スタジオが新UI提案・サイト改修実務を担当。博報堂が全体統括としてプロデュースを行います。
対面でもリモートでも対応可能なこちらのソリューションは、サイトの診断から実装までを一気通貫で対応させていただくことによって、相談窓口を博報堂に一本化することが可能です。特に診断領域においては担当するミライロ社とのタッグを組むことにより、以下のような強みがあります。
- Webアクセシビリティの専門家の目視によるJIS診断により、動作確認も含めた完全なチェックが可能
- さらに障がいのある方のモニター登録数が国内最大級であるため、障がいの種別や状態など多様な条件に対応したモニター診断が可能
- ミライロ社から提供する診断結果は、具体的な修正方法まで提示され、修正作業指示書としても活用可能
SDGs活動の第一歩としてWebアクセシビリティの改善から始めてみては?
Webアクセシビリティの診断チェックで引っかかるポイントは、ごく簡単なところばかりです。しかし、そこで大切なことは、世の中にはさまざまな人がいて、その誰もがインターネットやアプリを利用しているのだということをしっかり意識して、利用しようと思ったらすぐに利用できる環境を整備することです。
最近はテレビや新聞で「SDGs」関連の情報に触れない日はないといっても過言ではありません。しかし、自社は何から始めればよいか分からないという方も少なくないでしょう。
そういった悩み事を抱える企業は、簡単に始められる自社サイトのダイバーシティ対応として、まずはWebアクセシビリティの改善から始めてみてはいかがでしょうか?
今年の4月からいよいよ改正障害者差別解消法がスタートします。Webアクセシビリティに取り組もうと思ってまだ取り組めていない方や、Webアクセシビリティを確保したいがどのように始めたらよいかわからないという方は、本記事に記載したポイントを元に取り組むことをおすすめします。
博報堂グループでは、企業のダイバーシティ推進を支援する「WEBアクセシビリティ改善ソリューション」を提供しています。ユニバーサルデザインのリーディングカンパニー「ミライロ」と「博報堂アイ‧スタジオ」、「博報堂」の3社でタッグを組み、サイトの診断から改訂業務まで、ワンストップでご支援します。⇒サービス紹介ページはこちら

佐宗 謙一(さそう けんいち)
株式会社博報堂 ビジネス開発局 第二マーケットビジネスデザイン推進グループ
2007年博報堂入社。営業として大手飲料会社や自動車会社の広告制作業務、メディア業務を担当。途中博報堂DYメディアパートナーズへの出向経験もあり。2020年より現在のビジネス開発局に異動し、博報堂SDGsプロジェクトに参画し事務局を担当。